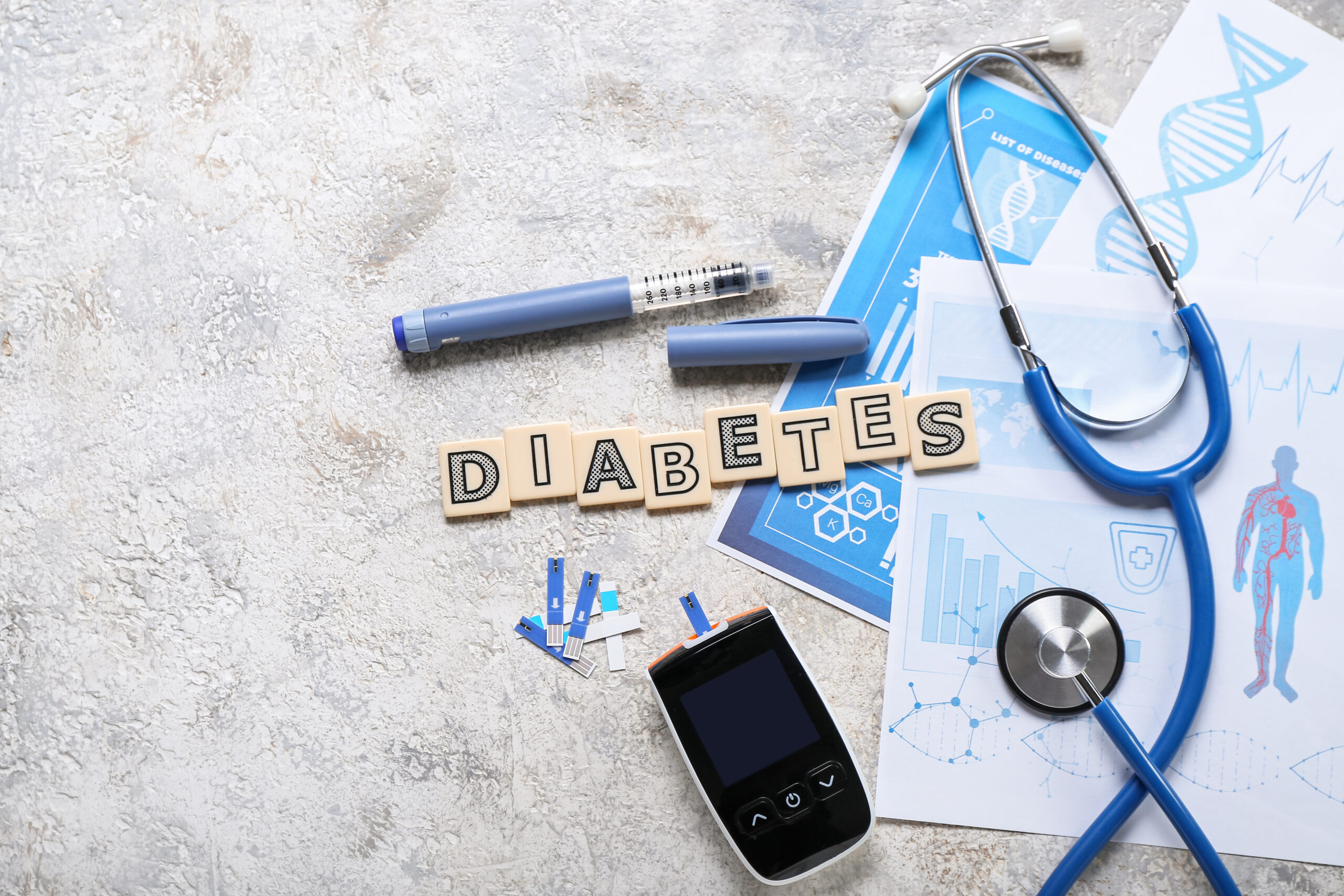糖尿病内科
Diabetology
糖尿病は、治療を継続して病気と上手に付き合うことで合併症を予防することができます。
糖尿病専門医の知見から、個々の患者様に合った
生活習慣の改善や適切な薬剤をご提案し、無理なく治療を継続できるように、治療方針を患者様と
ご一緒に考えさせていただきます。
病態により高次医療機関での精査、治療が必要と判断した場合には、速やかにご紹介いたします。
糖尿病がどのような病気か、その症状、治療について下記でご説明をしております。
糖尿病
どのような病気?
糖尿病とは、膵臓で作られるインスリンというホルモンの作用不足が原因で血糖値が高い状態のことを言います。インスリンの作用不足とは、インスリンの分泌が不十分であったり、インスリンの分泌は十分でもインスリンが効きにくい状態になったりすることを指します。
どのような症状がでる?
高血糖が続くと、喉の渇き、多飲、多尿、体重が減る、疲れやすいなどの症状が出現しますが、自覚症状がないことも多いです。また、高血糖の症状の他に、目が見えにくい、足が痛いなど、糖尿病の合併症の症状が先にみられる場合も多くあります。
糖尿病の合併症とは?
糖尿病は自覚症状がなくても、高血糖が続くと合併症が進行します。主な合併症は眼(網膜症)、腎臓(腎症)、神経(神経障害)が挙げられます。また、全身の動脈硬化が進行したり、白内障、サルコペニア(加齢に伴った筋力低下)、認知症、がんのリスク増加とも関連しています。
主な合併症である網膜症、腎症、神経障害についてご説明します。
糖尿病網膜症
目の中の網膜という組織が障害を受け、視力が低下します。進行すると手術によっても完治することが難しく、失明に至る場合もあります。病期は以下の4期に分類します。
①網膜症なし
②単純網膜症
③増殖前網膜症
④増殖網膜症
単純網膜症までは、血糖コントロール、高血圧の治療など内科的治療を行い、増殖前網膜症、増殖網膜症への移行を防ぎます。増殖前網膜症以上に進行した場合は、眼科医による治療が必要です。光凝固療法や手術を行う場合があります。
当院では、糖尿病と診断された時点で眼科への受診もお願いしています。合併症の進行を防ぐためには眼科の先生との連携が不可欠と考えています。
糖尿病性腎症
腎臓にある糸球体という毛細血管のかたまりが障害を受け、腎臓の機能が低下します。初期にはほとんど症状はありませんが、進行すると腎不全となり人工透析が必要になる場合があります。
病期は以下の5期に分類します。
①正常アルブミン尿期(第1期)
②微量アルブミン期(第2期)
③顕性アルブミン期(第3期)
④腎機能(GFR)高度低下・末期腎不全期(第4期)
⑤腎代替療法期(第5期)
病期は尿検査で判定します。腎症がある場合は、高血圧をコントロールすることで進行を遅らせることができます。第4期になると全身のむくみ、心不全などを併発することが多く、病態に応じて適切な時期に透析導入を行うことが必要となります。
糖尿病性神経障害
感覚神経の障害として、手や足がしびれる、痛くなる、感覚が鈍くなるなどの症状があります。感覚が鈍くなると、怪我をしていることに気が付かず、対処が遅れて潰瘍になったり、壊疽して切断に至る場合もあります。
運動神経障害として、障害された神経が支配する部位がうまく動かせなくなります。例えばまぶたや目が動きにくくなったり、手足の筋力が低下して転びやすくなったりします。
自律神経障害として、胃のむかつき、便秘や下痢、めまいや動悸の原因にもなります。また、痛みの機能が低下することにより、心筋梗塞が起こっても気が付かなかったり、不整脈を起こすなど、心臓の病気の原因になることもあります。
治療は血糖コントロールの目標達成を維持することです。自覚症状を改善し、神経機能の悪化を抑制するお薬を使うこともあります。
どのような治療がある?
食事療法
糖尿病の治療に食事療法は不可欠です。
体格(身長・体重)と活動量から適正なエネルギー量が決まります。適正なエネルギー量の範囲内でバランスの良い、規則正しい食事をすることが基本となります。腹八分目にする、バランスよく食べる、朝昼夕に規則正しく摂る、ゆっくりよく噛んで食べる、間食に気を付けるなど毎日のちょっとした心がけが大切です。
運動療法
運動をすることで、血糖値が下がったり、インスリンが効きやすくなったりする効果があります。重症の糖尿病や、合併症が進行している場合、運動療法は避けたほうがいいこともありますので、病態や年齢によって適切な運動量が異なります。具体的には、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動や筋力トレーニングを毎日無理せず続ける、日常生活の活動量を上げるなど、無理せず続けられる運動を行います。
薬物療法
糖尿病の薬にはいろいろな種類があります。薬の種類としては、飲み薬と注射の薬があります。飲み薬にはインスリンの分泌をよくする薬、インスリンの効きをよくする薬、糖の吸収や排泄を調整する薬があります。
注射の薬には、インスリンそのものを補う注射とインスリンの分泌を調節する注射があります。
糖尿病専門医の知見から、患者様の病態や生活スタイルに合ったお薬をご提案させていただきます。